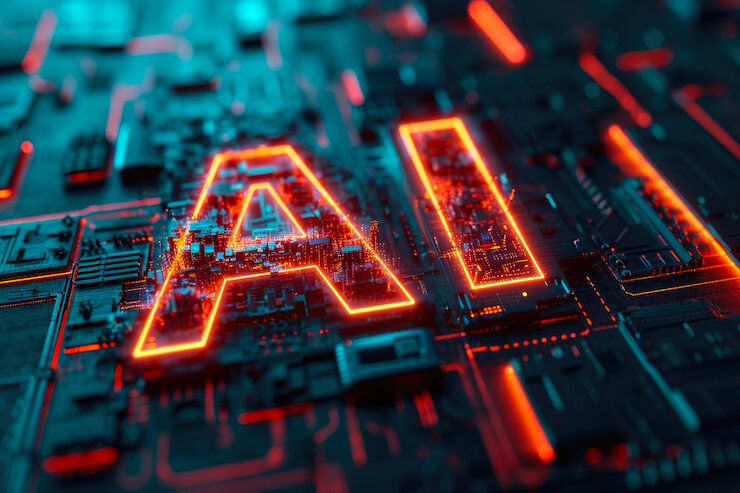Microsoft Copilot(コパイロット)とは?定義から主要機能・活用シーン・PC選定まで解説
ChatGPTの登場により生成AIが身近になった現在、同じく生成AIを活用したMicrosoft社の「Copilot(コパイロット)」も多くの企業で導入が進んでいます。
本記事では、Copilotの基本から料金プラン、実際の活用シーンまで、ビジネス導入を検討する際に必要な情報をわかりやすく解説します。※ 主にビジネス利用を想定したCopilot ProおよびMicrosoft 365 Copilotの機能を中心に紹介しています。
1. Copilotとは?
Copilotは、Microsoft社が提供する「AIアシスタント」で、業務効率化を目的とした業務支援AIツールです。ここではCopilotの基本情報について解説します。
1-1. Copilotの定義
CopilotはOpenAI社のGPTなどをベースとした大規模言語モデルを活用しており、自然言語処理技術によってユーザーの業務をサポートします。「Copilot(副操縦士)」という名前が示すとおり、人間の作業を補助するパートナーとしての役割を担っています。最大の特徴は、Microsoft 365製品との深い連携が可能な点です。
1-2. Copilotの特徴
Copilotの主要な特徴として、以下の3つが挙げられます。
既存のワークフローとの完全統合
Microsoft 365のWordやExcelといったアプリケーション内で直接AI機能を利用できるため、作業を中断することなく効率化できます。別のツールを立ち上げたり画面を切り替えたりする手間が不要で、集中力を維持したままスムーズに業務を進められる点が大きな強みです。
高度な文脈理解によるインテリジェントな支援
作業中の文書やデータの内容を理解し、状況に応じた最適な提案を行います。単なる文字処理にとどまらず、業務の目的や背景を踏まえた、一歩先を見据えたサポートを提供します。
複数アプリケーションを横断した統合的な作業支援
プロジェクトで必要となる複数アプリケーション間の情報連携を自動化します。たとえば、Teamsの会議内容をもとにExcelで分析データを作成し、PowerPointで一貫性のある資料にまとめるといった、シームレスな作業を支援します。
1-3. CopilotとChatGPTの違い
CopilotとChatGPTは同じGPTモデルをベースとしているため、何が違うのかと疑問に思う方もいるはずです。ここでは、これらの主な違いを比較してみましょう。
利用形態と連携性の違い
Copilot: Microsoft 365アプリケーション内に組み込まれており、WordやExcelで作業中に直接AI機能を呼び出せます。既存の業務フローを変えることなく、自然にAI支援を受けられる点が最大の特徴です。
ChatGPT: ブラウザまたは専用アプリでアクセスする独立したサービスとなっています。他のアプリケーションとの連携にはAPI利用やコピー&ペーストが必要で、別途作業が発生します。
情報取得と回答の特性
Copilot: リアルタイムでWeb検索を行い、最新情報を含む回答を提供します。回答には出典リンクが自動で付与されるため、情報の確認や裏付けを取りやすくなっています。
ChatGPT: 基本的には学習済みデータを基に回答を生成しますが、最新版ではリアルタイムのWeb検索機能も利用可能です。ただし、基本的には蓄積された知識による応答が中心となる傾向があります。
設計思想と適用場面
Copilot: ビジネス業務の効率化を目的に設計されており、文書作成、データ分析、会議要約など実務に直結するタスクに最適化されています。正確性と実用性を重視した構造化された出力を得意とします。
ChatGPT: 汎用的な対話AIとして開発されており、創造的な文章生成、アイデア発想、学習支援など幅広い用途に対応可能です。柔軟で自然な会話形式の応答を通じて、多様なニーズに応えることができます。
2. Copilotの主要機能と活用シーン
Copilotの具体的な機能と、ビジネスでの活用方法について解説します。
2-1. 主要機能
Microsoft 365アプリとの連携機能
Copilotの最大の特徴となる機能です。WordやExcel、PowerPoint、Outlook、Teamsなどのアプリケーション内で直接AIの支援を受けられます。作業中のファイルを離れることなく、その場でAI機能を呼び出し、文書作成やデータ分析を効率化できるのが魅力です。
文章生成・編集機能
自動で文章の作成、要約、校正を行います。ゼロから文書を作成するだけでなく、既存文書の改善提案や表現の最適化も可能です。ビジネス文書からメール文まで、用途に応じた適切な文体で生成されるため、文章作成の負担を大幅に軽減できます。
データ分析・可視化機能
数値データから自動でグラフを作成し、トレンド分析や予測を行います。複雑な関数やピボットテーブルの作成も自然言語で指示でき、専門知識がなくても高度なデータ分析が可能です。
画像生成・編集機能
DALL-E 3を活用して、テキスト指示から画像を生成できます。プレゼンテーション用の図表やイラスト作成に役立ち、既存画像の内容理解や説明も行えます。視覚的な資料作成の効率化に大きく貢献するでしょう。
検索・情報収集機能
Bing検索と連携してリアルタイムで最新情報を取得し、出典付きで回答を提供します。信頼性の高い情報源を自動で特定し、ファクトチェックの手間を軽減します。
2-2. 部門別の活用シーン
営業部門
顧客提案書の作成、競合分析資料の作成、営業レポートの自動生成などに活用できます。顧客情報をもとにパーソナライズされた提案書を作成したり、売上データの分析によって戦略立案を支援したりすることで、営業活動の質と効率を同時に向上させます。
企画・マーケティング部門
キャンペーン企画書の作成、市場分析レポートの生成などで効果を発揮します。最新のトレンドデータの分析や競合調査を効率化することで、戦略的な企画立案をサポートします。企画のアイデア出しから実行計画の策定、効果測定まで、幅広い場面で活用可能です。
カスタマーサポート部門
FAQ文書の作成、問い合わせ対応の下書き作成に利用できます。過去の対応履歴をもとに適切な回答案を提示し、一貫性のある高品質な顧客対応を実現します。
なお、Copilotの詳しい使い方については以下の記事で解説しています。Microsoft Copilotの使い方‐初心者向け基本操作から業務活用、プロンプト例まで
3. Copilotの料金体系と無料・有料プランの比較
Copilotの料金体系と、主なプランの特徴について解説します。
3-1. 無料プランの機能と制限
無料プランのCopilotは、GPT-4 Turboを使用してWeb検索、文章生成、画像生成、質問応答などの基本機能を利用できます。ただし、Microsoft 365製品との連携はできず、利用回数や商用利用には制限がある点に注意が必要です。
3-2. 各有料プランの機能と違い
有料プランである「Copilot Pro」と「Microsoft 365 Copilot」の詳細と違いを紹介します。
※ 本記事は2025年9月時点の情報をもとに作成しています。Copilotの料金等の最新情報については、Microsoftの公式サイトをご確認ください。
Copilot Pro(個人向け)
月額3,200円(2025年9月現在)で利用でき、一部のMicrosoft 365製品と連携可能です。利用回数制限も緩和され、個人事業主や小規模チームの業務効率化に適しています。WordやExcelでの文書作成効率が大幅に向上するでしょう。
Microsoft 365 Copilot(法人向け)
月額4,497円〜(2025年9月現在)で、全てのMicrosoft 365製品とCopilotを連携できます。管理者による利用制御やセキュリティ機能が含まれ、企業規模での導入に必要なガバナンスを確保できます。SharePointとの連携により、社内データ活用も円滑に行えます。
まとめると、試用・学習目的なら無料版、個人の業務効率化ならCopilot Pro、社内での本格導入ならMicrosoft 365 Copilotが適しています。
4. Copilotを使うメリットと注意点
Copilot導入のメリットと、利用上の注意点について解説します。
4-1. Copilot導入のメリット
資料・文章作成の自動化による効率化
提案書、議事録、プレゼンテーション資料などの作成を大幅に効率化でき、従来は数時間かかっていた作業を数十分程度で完了できる場合もあります。テンプレートを活用することで、企業の文書スタイルに合わせた一貫性のある資料作成が可能となり、品質向上と時間短縮の両方が期待できます。
専門知識がなくても高度な作業が可能
複雑なExcel関数の作成やデータ分析を自然言語で指示できます。プログラミングやマクロの知識がなくても分析結果を得られるため、スキルレベルに関係なく生産性を高められます。
発想・情報整理の支援による質の向上
ブレインストーミングや論点整理、多角的な視点の提示により、より質の高いアウトプットを得られます。会議準備では議題の整理や想定質問の洗い出し、プロジェクト計画ではリスク要因の抽出や代替案の提示など、包括的な計画立案を支援します。
このように、Copilotは単なる効率化ツールにとどまらず、業務の質を高めるパートナーとなります。文書作成からデータ分析、アイデア発想まで幅広く活用でき、働き方そのものを変革する可能性を秘めています。
4-2. 注意点と対策
情報漏えい・セキュリティリスク
機密情報や個人情報をCopilotに入力すると、情報漏洩のリスクがあります。情報漏えい防止ツールであるDLP(Data Loss Prevention)の導入や、利用ガイドラインの策定により、適切なデータ管理を徹底することが重要です。
社内設定・権限管理の不備
CopilotはSharePointやOneDriveのデータにアクセスするため、不適切な権限設定により部門を超えた情報共有が発生する恐れがあります。導入前に既存のアクセス権限を見直し、必要最小限の付与を徹底してください。
出力内容の正確性の限界
AIが生成する内容には誤りが含まれる可能性があります。重要な業務や意思決定に関わる文書では、必ず人による最終確認とファクトチェックを行ってください。特に法的文書、財務資料、契約書などでは専門家による検証を必須とし、AI生成内容をそのまま利用するのは避けましょう。
このように、Copilotは単なる作業効率化ツールにとどまらず、業務の質そのものを高める強力なパートナーとして働き方を大きく変える可能性を秘めています。
5. Copilot活用に適したPCは?
Copilotを効果的に活用するためのPC環境について解説します。
5-1. 必要なスペックと「Copilot+ PC」
Copilot in Windowsは、現在Windows 11を搭載しているほとんどのPCで利用可能です(管理者設定やバージョンによる制限がある場合を除く)。Windows 11 Pro搭載の最新PCにはあらかじめプリインストールされており、利用者は追加費用なくすぐに使い始められます。つまり、基本的なCopilot機能であれば、Windows 11搭載PCさえあれば利用できます。
ただし、より快適かつ効率的に使う場合や、高度なAI処理を伴う業務では、PC環境を見直す価値があります。
Copilot+ PCとは
Microsoftが定める新基準「Copilot+ PC」は、AI活用に最適化された次世代Windows PCです。通常の「Copilot」が主にクラウドサーバー側で処理されるのに対し、「Copilot+ PC エクスペリエンス」ではPC本体のハードウェアを用いてローカルで実行できる点が大きな違いです。
Copilot+ PCの要件と特徴
Copilot+ PCとして認定されるには、以下の要件を満たす必要があります。
NPU(Neural Processing Unit) 毎秒40兆回以上の演算(40TOPS以上)を処理可能なAI専用プロセッサー。これにより、クラウドに依存せずプライバシーを守りながら、低遅延で高速なAI処理が実現できます。メモリ ストレージ
これらの要件により、ペイントのコクリエーター、Windowsスタジオエフェクト、ライブキャプション、リコールなどの専用AI機能が利用可能になり、GPUよりも低消費電力で効率的な処理が実現されます。
5-2. PC選択の指針と調達のポイント
PC選択の指針
日常的な文書作成、メール送受信、Web検索といった基本的な業務であれば、一般的なWindows 11搭載PCで十分対応できます。 一方で、本格的なデータ分析や画像生成、複数アプリの同時利用を中心に行う環境では、Copilot+ PCの導入が推奨されます。AI処理の高速化や省電力性を体感でき、将来的な機能拡張にも対応できるためです。
主要対応メーカー
Copilot+ PC対応機種は、Microsoft Surfaceをはじめ、Acer、ASUS、Dell、HP、Lenovo、Samsungといった主要OEMパートナーから提供されています。各メーカーが独自の強みを活かした製品を展開しており、用途に応じた選択が可能です。
調達のポイント
法人でのPC導入では、初期コストの抑制、機器更新の柔軟性、運用管理の効率化が重要な検討要素です。しかし、最新のAI対応PCは高性能な一方で導入コストが高額になる傾向があり、機器更新の妨げとなりがちです。また、導入コストが高いということは故障時のリスクもそれに伴って上昇することになります。PCレンタルやPCLCM(PCライフサイクルマネジメント)サービス の活用です。
まとめ
Microsoft Copilotは、大規模言語モデルをベースとした業務支援AIツールとして、Microsoft 365製品との連携により業務効率化をサポートします。文書作成の自動化、データ分析の簡素化など、日常業務の多くの場面で時間短縮と品質向上が期待できます。無料版から利用開始でき、個人向けのCopilot Pro、法人向けのMicrosoft 365 Copilotまで、ニーズに応じたプランが用意されています。
ただし、Copilotを最大限に活用するには適切なPC環境が不可欠です。そこでCopilot導入を検討している企業には、三菱HCキャピタルITパートナーズのPCレンタル・PCLCMサービス をおすすめします。最新スペックのPC提供から運用支援まで、専門家が効果的なAI活用環境の構築をサポートします。
Copilot活用、それに伴う新たなPC調達をご検討の際は、ぜひ当社にご相談ください。
三菱HCキャピタルITパートナーズのPCLCMサービス
法人PCのレンタルがおすすめな理由とは?
PCの調達手段に悩む管理担当者様へ。「レンタル」と「リース」の違いや、PC運用管理業務の負担を軽減できる「レンタル」についてご案内します。
関連サービス資料
法人PCのレンタルがおすすめな理由とは?