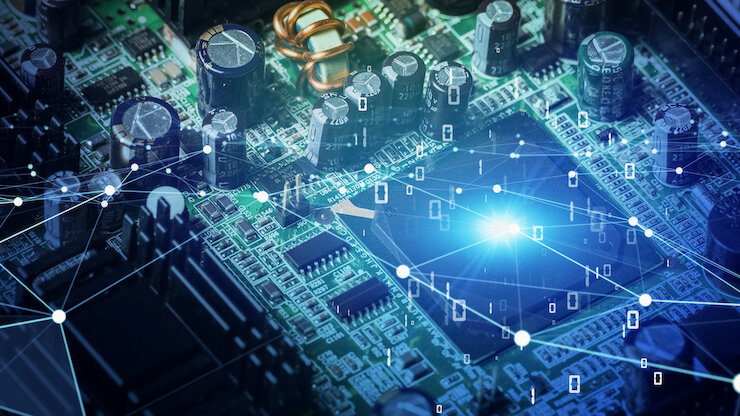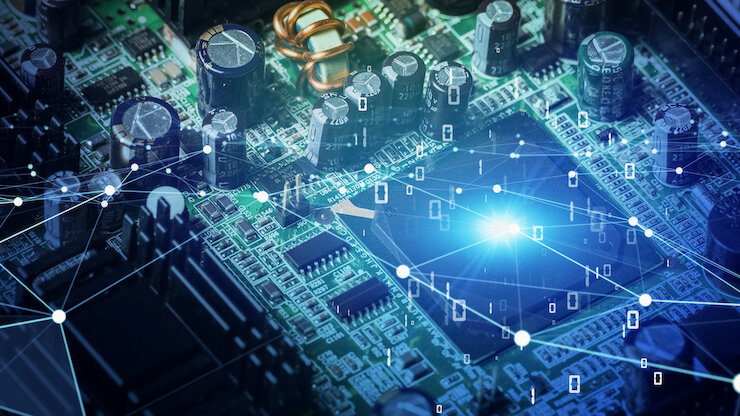Intel CPUの世代の特徴と見分け方 - 法人PC調達担当者が知るべき選定ポイント
企業のPC一斉リプレースにおいて、ビジネス要件を満たす最適なCPU選定は重要なポイントです。Intel CPUは近年大きな変化を遂げており、この変化が企業のPC調達戦略にどのような影響をもたらすのか理解する必要があります。
本記事では、業務要件に適したCPU世代の選択がもたらす効果と、想定使用期間内での性能維持の重要性について解説します。
1. Intel CPUの世代の変遷とAI処理能力の進化
Intel CPUは各世代で処理性能の向上に加え、特にAI処理能力の強化が注目されています。この進化を理解することで、今後のビジネス環境でのAIテクノロジー活用を見据えた最適なハードウェア選定が可能になります。
1-1. 初期世代からの進化(第1〜7世代)
第1世代から第7世代まで(2008〜2017年)は、処理性能の向上と電力効率の改善が主な進化でした。この時期のCPUはAI処理に特化した機能はまだ搭載されていませんでしたが、基礎的な計算処理能力の向上がなされました。
1-2. AIサポート機能の萌芽(第8〜11世代)
第8世代(2017年)以降、マルチコア化が進み並列処理能力が大幅に向上。特に第10世代では一部モデルにAI処理向け命令セットが追加され、第11世代(Tiger Lake)ではIntel Xeグラフィックスの導入によりAI処理能力が強化されました。
1-3. ハイブリッド構造による効率化(第12〜14世代)
第12世代(2021年)からは高性能コア(P-core)と高効率コア(E-core)を組み合わせるハイブリッド構造が採用され、複数のAI処理タスクを同時に効率よく処理できるようになりました。
1-4. AI専用プロセッサの標準搭載(Core Ultra)
2023年から始まった「Core Ultra」シリーズでは、AI処理を専門に行うNPU(Neural Processing Unit)が標準搭載され、ビジネスシーンでのAI活用が格段に容易になりました。従来のCPUやGPUを使ったAI処理と比較して、NPUは低消費電力でAI処理を実行できるため、モバイル環境でのAI活用が現実的になっています。
2. CPU世代の識別方法
2-1. 型番からCPU世代を見分ける方法
Intel CPUの型番は一見複雑ですが、基本的なルールを理解すれば世代を判別できます。2023年の第14世代までは「Core i」シリーズ(例:Core i5-13600K)という表記が使われていましたが、2024年以降は「Core」および「Core Ultra」シリーズ(例:Core 7 150U、Core Ultra 7 165H)に刷新されています。
旧世代(第14世代まで)の型番例
例:Core i5-13600K
- 「Core i」:シリーズ名
- 「i5」:グレード(i3、i5、i7、i9の順で高性能)
- 「13」:世代
- 「600」:性能ランク
- 「K」:特性を表すサフィックス*1(Kはオーバークロック*2可能)
新世代(2024年以降)の型番例
例:Core 7 150U、Core Ultra 7 165H
- 「Core」または「Core Ultra」:シリーズ名
- 「7」:グレード(5/7/9の順で高性能)
- 「150」や「165」:SKU(性能ランク)
- 「U」「H」など:サフィックス*1(用途や特性を表す。Uは省電力、Hは高性能モバイル向けなど)
現行のIntel CPUは、「Core」および「Core Ultra」シリーズに分類され、用途や求める性能に応じてグレード(Core 5、Core 7、Core 9、Core Ultra 5/7/9など)が選択されます。たとえば、Core 5は一般的な事務作業やWeb閲覧などのエントリー〜ミドルレンジ用途に適しており、Core 7やCore Ultra 7はデータ分析や開発業務、動画編集など高負荷な作業にも対応できる高性能モデルです。
*1 CPUモデル番号の末尾につく英字記号で、特定の機能や特性を示します。
*2 CPUの動作周波数を製造元が設定した標準値より高く設定することで、処理性能を向上させる技術です。ただし発熱量増加や電力消費の増大、部品寿命への影響があるため、企業PCでは通常使用されません。
2-2. 既存PCのCPU世代を確認する方法
既存PCのCPU世代を確認するには、Windowsなら「システム情報」ツールを開き、「プロセッサ」の項目を確認します。正確な世代番号が表示されない場合は、型番をメモしてIntelの公式サイトで確認するとよいでしょう。
2-3. 大量PCのCPU情報を効率的に収集する方法
企業環境で数百、数千台のPCのCPU情報を効率的に収集するには、専用ツールの活用が欠かせません。
- IT資産管理ツール:Microsoft Intuneや Microsoft Configuration Manager(MCM)、LANSCOPEなどの国内でも広く利用されている資産管理ツールを使えば、ネットワーク内のすべてのPCから自動的にハードウェア情報を収集できます。
- 統合的なIT資産管理プラットフォーム:CPU情報の収集に加え、ソフトウェアライセンス管理やセキュリティ状況の一元監視、さらにはリプレース計画の策定まで一貫して行えるプラットフォームの活用も効率的です。これにより、収集したデータを分析して部門ごとの最適なPC構成の検討や将来的な投資計画の立案に役立てることができます。
3. Core Ultraの主な特徴
2023年末に導入されたIntelのCPU体系の大きな変化として、従来のCore iシリーズからCore Ultraシリーズへの移行があります。この変化は単なる名称変更ではなく、企業PCの性能や運用に具体的な効果をもたらしています。2025年現在、多くの企業向けPCにCore Ultraが標準搭載され、ビジネスユーザーの生産性向上に貢献しています。
3-1. 主要な技術革新
- タイルベース設計:複数の処理ユニットを1つのパッケージに統合する設計により、効率的な処理が可能になりました。
- NPU搭載:AI処理を専門に行うプロセッサが標準搭載され、AI機能を活用したアプリケーションのパフォーマンスが向上しています。
- 電力効率の改善:Intel 4製造プロセスの採用により、同じ性能を発揮するのに必要な電力が削減され、特にノートPCではバッテリー持続時間の延長が期待できます。
3-2. ビジネス利用におけるメリット
- AI機能の業務活用:Microsoft CopilotなどのAIアシスタントが高速で動作し、会議の文字起こしやデータ分析、資料作成の補助に活用でき、業務効率が大幅に向上します。
- 省電力性能による運用コスト削減:特にモバイルワーカーにとって重要なバッテリー持続時間が大幅に改善され、外出先での充電の心配が減少しました。これにより移動中や会議中の生産性が向上するとともに、バッテリーの劣化が遅くなることでPCの実質的な使用可能期間も延長され、リプレースサイクルの最適化にもつながります。
- セキュリティ強化:最新の暗号化技術や保護機能を備え、Intel vPro搭載モデルではハードウェアレベルでのセキュリティ機能が強化されています。
4. 企業のPC調達におけるCPU世代選定のポイント
4-1. 業務用途に合った性能選び
- 一般事務作業向け:文書作成やWeb閲覧、メールなどの基本業務が中心となる場合、Core i5の第11世代以降、あるいはCore Ultra 5であれば十分な性能を発揮します。
- クリエイティブ業務・開発業務向け:画像や動画編集、CAD操作、プログラミングなどを行う部署では、Core i7の第12世代以降、またはCore Ultra 7がおすすめです。
- モバイルワーカー向け:社外での利用が多いユーザーには、バッテリー持続時間が重要です。Core Ultraシリーズのモバイル向けモデルは、電力効率が大幅に向上しているため、長時間の外出先での利用に適しています。
4-2. コストと性能のバランス
- 世代間の価格差と性能差:最新世代のCPUは将来的な拡張性や長期利用を考慮すると最も適切な選択肢です。一方で、限られた予算内でIT投資を最適化する必要がある場合、1世代前のCPUも選択肢として考慮できますが、パフォーマンスの向上と想定使用期間を踏まえた選定においては、基本的に最新モデルが推奨されます。
- 旧世代品活用のリスク:CPUやデバイスドライバのメーカーサポート期間が短くなることや、将来的なソフトウェア要件に対応できなくなる可能性があります。特に次世代OSへの移行を見据えると、比較的新しい世代のCPUを選ぶことが望ましいでしょう。
- 企業規模別の最適戦略:業務の効率化を優先する部門には最新世代を、コスト効率を重視する部門には価格性能比の高い1世代前のモデルを、といったように、部門ごとの要件に合わせた選定が効果的です。一方で、保守管理の効率化のためには、企業全体でPC構成を標準化することも検討価値があります。
4-3. 将来の互換性を見据えた選定
- OSやアプリケーションの互換性:各世代の新OSでは、前世代と比較してハードウェア要件がより厳格になる傾向があります。これはWindows 7からWindows 10、そしてWindows 11への移行でも見られた傾向です。長期的な使用を見据えると、最新の要件に余裕を持って対応できるCPUを選ぶことが賢明です。
- 計画的移行:全社的なPCの棚卸しを行い、次期OSの動作要件を満たさない機器、要件は満たすがパフォーマンスに不安がある機器、問題なく対応可能な機器に分類し、部門ごとの優先度を設定した段階的な移行計画を立てることが重要です。
4-4. 自社のIT戦略を考慮した選定
- 全社的なデジタル変革計画との整合性: CPU選定は、企業全体のデジタル変革計画や業務効率化目標と連動させることが不可欠です。例えば、リモートワーク推進やペーパーレス化など、具体的なIT施策の実現に必要な処理能力を評価し、3〜5年の利用を見据えた余裕あるスペックを選定するとよいでしょう。また、部門間でのデータ連携や分析業務が増加する傾向を踏まえ、将来的なワークフローの変化にも対応できる処理能力を確保することが望ましいといえます。
- セキュリティリスク管理:最新世代のCPUには、セキュリティ脆弱性対策がハードウェアレベルで実装されています。例えば、第8世代以降のIntel CPUでは、「Meltdown」や「Spectre」といった脆弱性に対するハードウェアレベルでの対策が施されるようになり、第11世代以降ではControl-flow Enforcement Technology(CET)によるマルウェア対策が強化されています。Core Ultraでは、機密データ保護機能がさらに強化され、仮想化技術による隔離機能も向上しています。こうした機能は機密情報を扱う部門のセキュリティリスク低減に直結するため、これらの部門には優先的に最新世代を導入することを検討すべきです。
- クラウド基盤との連携:効率的なクラウドサービスとの連携のためには適切なクライアントデバイスの選定が欠かせません。特にAI機能を活用したクラウドサービスが増加している現在、NPU搭載のCore Ultraシリーズは将来的な拡張性の観点から検討価値があります。
まとめ
企業のPC調達担当者にとって、CPU世代の理解は適切なパフォーマンスと投資対効果を両立させるための重要な判断基準です。CPU世代の選定は、日常業務のパフォーマンス向上だけでなく、業務内容に応じた適切なCPU世代を選ぶことで過剰投資を避けながら必要十分な性能を確保できます。大規模なPC調達では、適切な性能選定による1台あたりのコスト最適化が全体で大きな節約につながります。
また、新技術への対応力を持った適切な世代のCPUを選ぶことで、PCの使用可能期間が延び、リプレースサイクルを最適化できるため、調達コストの分散と削減につながります。特にAI処理性能が強化されたCore Ultraのような最新世代のCPUは、新しい業務ツールの活用を通じて生産性向上に貢献し、人的リソースの最適化にもつながるでしょう。大規模なPC導入やリプレースを控えている企業では、こうしたメリットを最大化するための適切なCPU世代選定と計画的な導入が求められます。Core Ultraへの移行は、AI機能や省電力性能など新たなビジネスメリットをもたらします。企業のIT戦略全体を俯瞰した場合、PCのスペック選定はより大きなIT投資戦略の一部として捉えることが重要です。
三菱HCキャピタルITパートナーズでは、IT機器とセキュリティに精通した専門知識を活かし、お客様のデバイス調達からセキュリティ対策まで一貫したIT戦略構築をサポートしています。適切なデバイス選定や効率的なIT資産運用についてお悩みの際は、ぜひご相談ください。