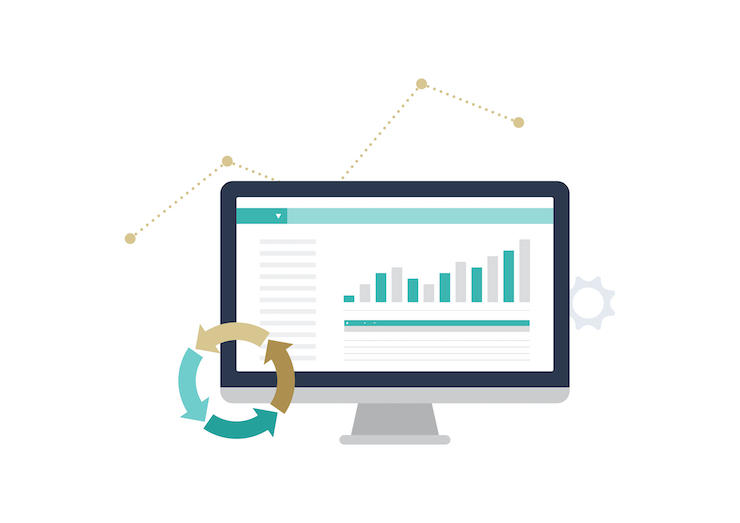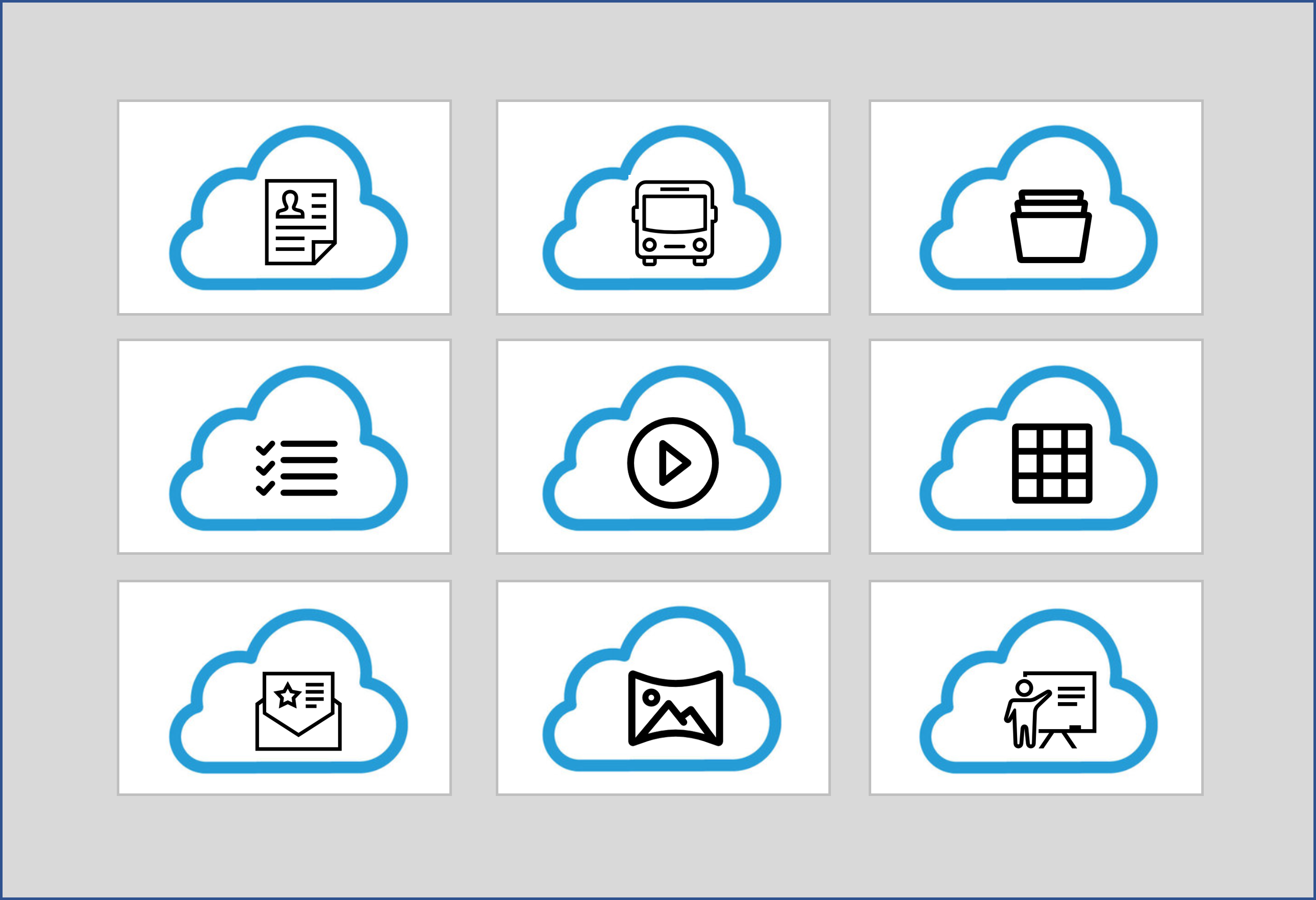ハイブリッドワークとは?メリット・デメリットや導入のポイントを紹介
いまや新しい働き方として定着したテレワーク。現在も多くの企業がその継続を掲げています。テレワークは通勤時間を節約できる、プライベートと仕事のバランスを取りやすいといったメリットがある半面、全ての業務をテレワークに置き換えることが難しい職種や、出社しなければ円滑に進まない業務もあります。
こういった問題への解決策として生まれたのが、「ハイブリッドワーク」という働き方です。ハイブリッドワークはテレワークとオフィスへの出社を組み合わせた働き方で、 多用な業務形態への対応と従業員の働きやすさを両立するために注目を集めています。
本記事では、ハイブリッドワークの意味やメリット・デメリット、ハイブリッドワークでの働き方を成功に導くためのポイントを解説します。
ハイブリッドワーク導入のため、PCLCMサービスをご検討されている方は、こちらもあわせてご確認ください。
➡【資料ダウンロード】PC運用にお悩みの担当者必見 PCLCMサービス導入ガイド
ハイブリッドワークとは?
ハイブリッドワークとは、従来の出社を伴うオフィスでの勤務と自宅やシェアオフィスなどで働くテレワークとを融合させた勤務形態です。
従業員は業務の内容に応じて、 自由にオフィス勤務とテレワークを選択できます。この柔軟な働き方がハイブリッドワークの特徴であり、自由度の高い勤務スタイルとして注目されています。
ハイブリッドワークが広まった背景には、2019年に発生したコロナ禍においてテレワークだけでは補えない業務があったことが挙げられます。チーム作業やプロジェクトなどにおいては、オンラインだけでは重要な業務を進めるのが難しく、出社が必要な場面もありました。また、緊急対応を伴う業務では現場で働く従業員が必要であることからも、出社とテレワークを組み合わせたハイブリッドワークが有効な対応策として選ばれました。
さらに、コロナ禍の収束に伴い、出社して顔を合わせることが奨励されるようになったことも、ハイブリッドワークが導入される理由のひとつになっています。
ハイブリッドワークのメリット
ハイブリッドワークには、勤務形態を組み合わせることによる業務効率の向上のほか、人材を確保しやすくなる、緊急時のリスク低減などのさまざまなメリットがあります。以下に詳しく解説します。
勤務形態を組み合わせることで効率が上がる
ハイブリッドワークには、業務の状況に応じて勤務形態を選択できるという利点があります。ひとりで集中して作業をしたい場合は在宅勤務を選び、チームでの作業がある場合は出社する、というように、状況に応じて使い分けることで作業効率を高めることが可能です。
また、出社して勤務した際はお互いに声をかけやすくなるため、話し合うことで疑問点を解決できたり、上司からの指示を理解しやすくなったりと、コミュニケーションの取りやすさからの効率アップが期待できます。
人材を確保しやすくなる
ハイブリッドワークの導入により、毎日出社する必要がなくなります。このことは、従業員にとって多様な働き方が可能になり、育児や介護といった家庭の事情などによるキャリアの中断を回避できるという大きな利点を生み出します。これによって従業員満足度も向上し、離職率の低下にもつながるでしょう。
他にも、今まで通勤距離や時間の事情に縛られていた採用枠を広げられるというメリットもあります。
また、働き方にメリハリをつけられるハイブリッドワークを希望する人材は多いため、求人広告でもアピールポイントとなります。企業にとって、ハイブリッドワークは人材確保面においてもメリットが大きいと言えるでしょう。
緊急時のリスク低減に役立つ
ハイブリッドワークは、災害や緊急事態発生時に業務がストップするリスクを回避することにも役立ちます。オフィスで業務ができない場合でも自宅で作業が可能であり、BCP(事業継続計画)において災害や緊急時に業務への影響を抑えて事業を継続させるための緊急時対応計画の一環になります。
どのような状況でも事業を継続させることは、社会的信頼性を向上させるためにも重要です。
ハイブリッドワークのデメリットとは
多くのメリットがあるハイブリッドワークですが、従業員の評価や勤怠管理が難しくなる、コミュニケーションの機会が少なくなるといったデメリットも存在します。
これらの問題点について解説していきます。
従業員の評価や勤怠管理が難しくなる
ハイブリッドワークでは、常にオフィスで勤務している場合と比べて勤務状況や業務の進捗の把握が難しくなり、そのため「適切な人事評価がされていない」と従業員のモチベーションの低下が発生することがあります。
そこで、ハイブリッドワークを導入する際は、出社時とテレワーク時、両方の勤怠管理ができるシステムやルールの整備が必要です。
コミュニケーションの機会が少なくなる
ハイブリッドワークでは、対面でのコミュニケーションの機会が制限されるため、情報共有や意思疎通において課題が生じる場合があります。常に従業員全員が職場にそろうわけではないため、出社頻度によって業務情報の把握に格差が生じます。適切なコミュニケーションツールや会議の設定などにより、これらの課題を解消する工夫が必要です。
ハイブリッドワークの導入を成功させるポイント
ここからは、ハイブリッドワークの導入を成功させるためのポイントを紹介します。前項で述べたハイブリッドワークの主なデメリットである、従業員の評価や勤怠管理、およびコミュニケーションに関する課題をいかに解決するかがポイントになります。
人事評価システムの導入
従業員の評価に関する課題には、ハイブリッドワークに適した評価システムの導入が必要です。業務達成度や工数管理など、出社時とテレワーク時の評価を適切に行うシステムを導入し、不公平を防ぐために人事評価制度を見直すことが重要です。
コミュニケーションスペースの整備
コミュニケーションを活性化するためには、カフェスペースや仕切りで区切ったコミュニケーションスペースなど、気軽に利用できる雰囲気のワークスペースを設置することが有効です。会議室と異なり予約をせずに利用できるため、ちょっとしたミーティングでもスムーズに行うことができます。
コミュニケーションツールの導入
Web会議、チャットなどのコミュニケーションツールは、遠隔地で勤務する従業員とのコミュニケーションや情報共有のために必須です。
さらにコミュニケーションの促進と情報共有の円滑化を図るために、情報共有のためのグループチャットを作ったり、報告や連絡のルールを共有したりするなどの仕組みづくりも大切です 。
また、従業員の勤怠管理や業務進捗共有、スケジュール共有などの各種専用ツールを導入することも効果的です。
ハイブリッドワークの運用ルールの制定
ハイブリッドワークの運用をスムーズに行うためには、適切なルール作りも必要です。テレワークの対象範囲、労働時間や場所、人事評価や業務報告の方法、勤怠管理などに関するルールを制定し、全従業員で共有しましょう。また、ルールは一度作成して終わりではなく、状況や要望に応じてアップデートしていくことが大切です。
ハイブリッドワークを導入し、より働きやすい環境に
ハイブリッドワークは、業務状況に応じて勤務形態を選べる魅力的な働き方です。他の働き方にはない柔軟性があり、業務効率の向上や人材の確保に貢献するだけでなく、緊急時のリスク低減にも役立ちます。
また、ハイブリッドワークは、テレワークのデメリットであるコミュニケーションの取りづらさや企業への帰属意識の希薄化といった課題にも対応できます。従業員の満足度を高める要素を多く備えているため、業務にも好影響が期待されます。
ハイブリッドワーク導入には、オフィス用のPCと、テレワーク用のPC、もしくはその両方を1台で補うモバイルPCの準備が必要です。当社のPCLCM(PCライフサイクルマネジメント)サービスなら、PCの調達から処分まで、ハイブリッドワーク導入を含めたお客様のニーズに応えるトータルサポートを提供します。ハイブリッドワーク導入の際は、ぜひ当社のPCLCMサービスをご検討ください。
関連サービス
PCLCMサービスメニュー
法人PCのレンタルがおすすめな理由とは?
PCの調達手段に悩む管理担当者様へ。「レンタル」と「リース」の違いや、PC運用管理業務の負担を軽減できる「レンタル」についてご案内します。